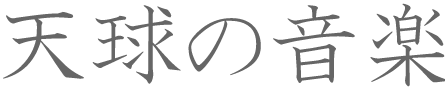


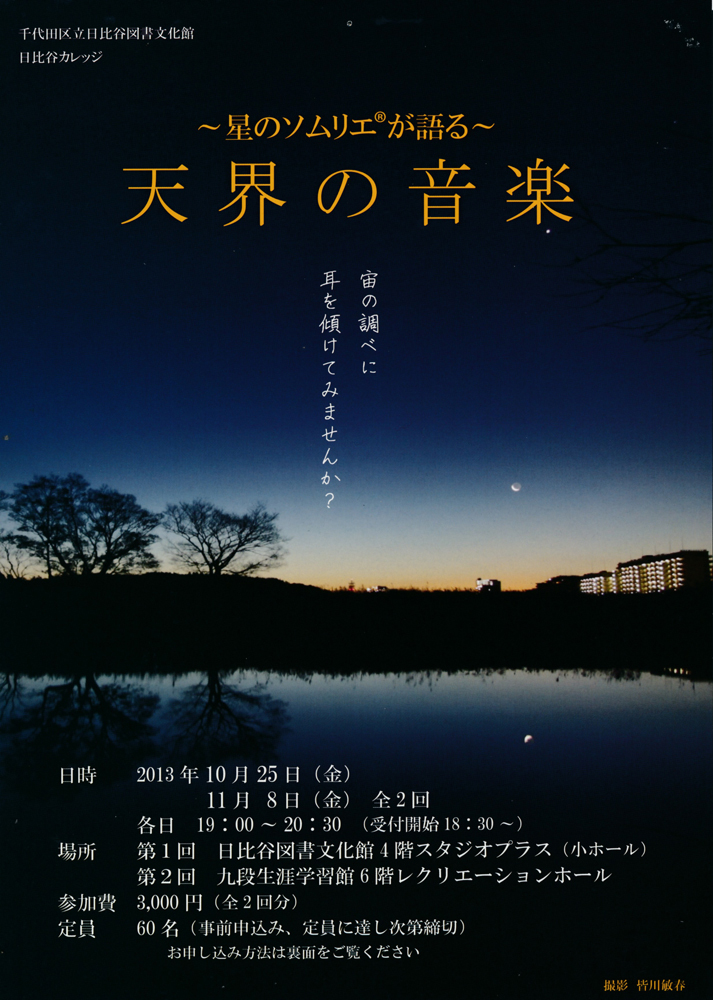 |
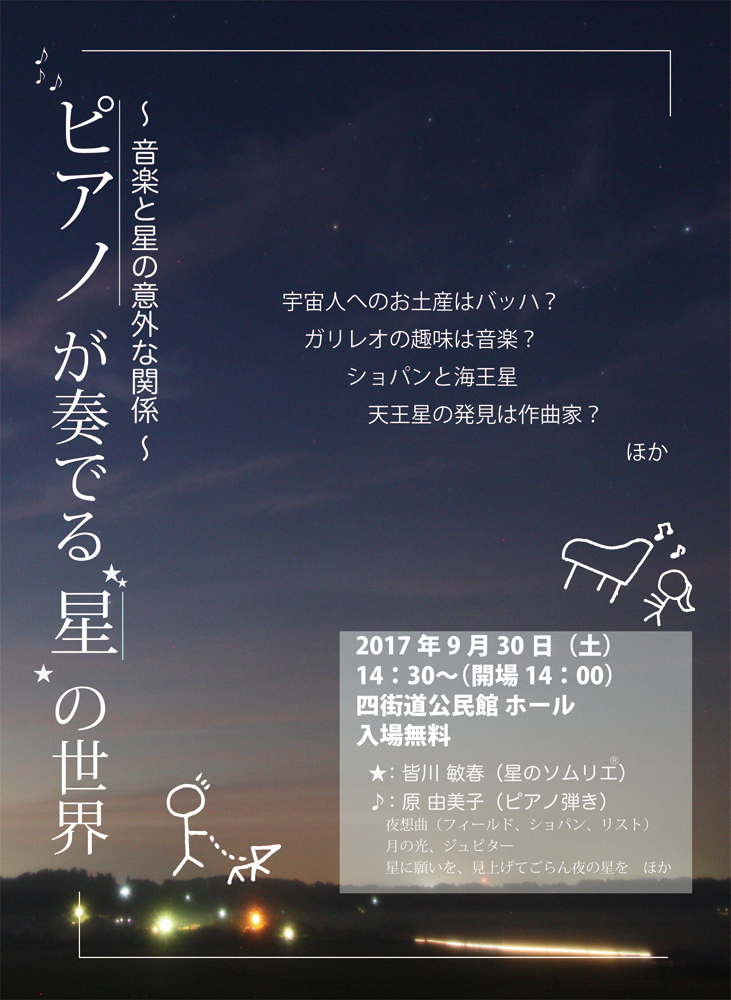 |
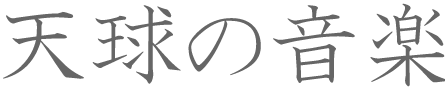 |
||
 |
||
 |
||
|
|
星の音楽、宇宙の響きというページ名にしてみましたが、特にクラシックの世界における、その手の「タイトル」の曲を集めてみました。中には、モロ、星空からインスピレーションを受けて作曲された曲もあり、興味は尽きません。 また、1900年に入ってからは、いわゆる現代音楽の中に宇宙・天文に関係するテーマが取り入れられていく傾向が強くなってきているようです。 私には現代天文学が、自らの観測結果から導いた「神の作った気まぐれな宇宙」という束縛から離れたことが大きく影響しているのでは?と思えます。 天体望遠鏡や写真などの観測結果や実験によって得られた姿から考察し、数学や物理などの世界が解く「無機質な宇宙の姿」の発見。それが通信手段の発達により世界中に届けられるようになり、それに呼応するかのように、感受性の豊かな作曲家たちが無調の音楽に傾倒していった… そんな風に思っています。 私は作曲家ではないので、そのイマジネーションはまったく関知するところではありませんが、「無機質の世界」と「無調の音楽」は相性がいい?そんなことを考えながら耳を傾けると、現代音楽も普通に(笑)聞くことができるようになりました。 ここでは、テーマが完全に星や宇宙とかかわりのあるもの、あるいはタイトルだけ借用してきたもの、作曲家の意に反して、のちの人が「らしい」タイトルを付けた曲までをご紹介します。 これらの曲を、実際に星空を眺めながら聴くもよし、宇宙論や星座(ギリシア神話など)に関する本を読むときのB.G.M.で聴くもよし。 随時追加中。 |
| 芸術作品は、芸術家が映す自然の鏡だから、必然的に芸術家が近くする通りの自然を反映するのは避けられないのではないでしょうか? その上、芸術家が宇宙論を主題として用いるばかりでなく(芸術作品は叙述体の実在描写であるばかりでなく)、芸術作品の形式もまた、彼の近くに寄る宇宙構成法の認識、結果を反映する。芸術作品の組織、その構造は実在の根本的な構成要素がどのように相互に関係しているかについての芸術家の見解を伝達する有効な手段である。作品の構造は、園見解の提示全体に寄与するし、中には顕著な特徴をなし、その提示の主要な手段になっている霊があるかも知れない。 |
『天球の音楽 - ピュタゴラス宇宙論とルネサンス詩学』より |

「星の音楽、宇宙の響き」というページ名に、情報がよせられて、こんなにも多くの作曲家が宇宙との繋がりを求めて「天球の音楽」を作曲していたとは、正直驚いてしまいました。一覧と言う形で、古代〜現代をひっくるめてリストアップしてきましたが、だんだん乱雑になってきてしまったため、年代毎にまとめることにしました。 |
気がつきませんか まわりで輝く無数の星を眺め 運動する天球が奏でる この世ならぬ調和の音を聞いて サファイアのように光り 星々を軌道に保っている |
ピエトロ・メタスターシオ (Pietro Metastasio, 1698-1782) |
芸術作品は、芸術家が映す自然の鏡だから、必然的に芸術家が近くする通りの自然を反映するのは避けられないのではないでしょうか? その上、芸術家が宇宙論を主題として用いるばかりでなく(芸術作品は叙述体の実在描写であるばかりでなく)、芸術作品の形式もまた、彼の近くに寄る宇宙構成法の認識、結果を反映する。芸術作品の組織、その構造は実在の根本的な構成要素がどのように相互に関係しているかについての芸術家の見解を伝達する有効な手段である。作品の構造は、園見解の提示全体に寄与するし、中には顕著な特徴をなし、その提示の主要な手段になっている霊があるかも知れない。 |
『天球の音楽 - ピュタゴラス宇宙論とルネサンス詩学』より |
曲名(原題) |
題材、編成など |
作曲家 |
||
明るい星々よ、煌きたまえ RV625(1715) Clarae stellae, scintillate |
作詞者不詳の宗教曲。邦訳には「明るく輝く星」も |
アントニオ・ヴィヴァルディ(1671-1751) Antonio Vivaldi |
||
しかし、なんという温和な星だろう(1720)+ Ma qual astro benigno |
歌劇「オルランド」Orlando |
ニコラ・ポルポラ(1686-1768) Nicola Porpora |
||
自然の諸原理に還元された和声論(1722) Traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels |
「音楽は音の科学である」というテーマで執筆された記念碑的理論書。当然ピュタゴラスに回帰 |
ジャン・フィリップ・ラモー(1683-1764) Jean-Philippe Rameau |
||
歌劇「惑星の調和」(1723) La concordia de' pianeti |
エリーザベト命名日の祝典劇。アポロとディアナの他に5つの惑星の神々が登場 [Dg; 4793356] |
アントニオ・カルダーラ(1670-1736) Antonio Caldara |
||
惑星公会議(評議会)(1729) Il Concilio De'pianet |
Girolamo Baruffaldiの台本。惑星の象徴である神々が登場し、フランス王の太子誕生を祝って作曲、上演。 |
トマゾ・アルビノーニ(1671-1751) Tomaso Albinoni |
||
天球儀と羅針盤を持つウラニア(1738) Uranie |
器楽曲。『音楽のパルナッソス』より第9曲 [NAXOS; 8554446] |
ヨハン・フィッシャー(1656-1746) Johann Caspar Ferdinand Fischer |
||
組曲「惑星の性質ないし本質」(1739?) Die Natur und Eigenschaft der Planeten |
楽譜が消失 |
ディートリヒ・ブクステフーデ(1637-1707) Dieterich Buxtehude |
||
皆既日食のようだ!(1741)+ Total eclipse!(Samson HWV 57) |
オペラ『サムソン』より |
ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル(1685-1759) Georg Friedrich Handel |
||
歌劇「月の世界」(1750) Il Mondo Della Luna |
カルロ・ゴルドーニ(1707-1793)台本の喜劇 |
バルダッサーレ・ガルッピ(1706-1785) Baldassare Galuppi |
||
歌劇「月の世界」(1762) |
ニコロ・ピッチンニ (1728-1800) Niccolo Vito Piccinni |
|||
歌劇「月の世界」(1765) |
ペドロ・アントニオ・アヴォンダーノ(1714-1782) Pedro Antonio Avondano |
|||
歌劇「月の世界」(1765) |
フローリアン・レオポルド・ガスマン (1729-1774) Florian Leopold Gassmann |
|||
交響曲第43番「マーキュリー」(1771) Symphonie No.43 |
出版社がつけたタイトルで実際には無題 |
フランツ・ヨーゼフ・ハイドン
(1732-1809) Franz Joseph Haydn |
||
音楽家から天文学者へ転職。 |
ウィリアム・ハーシェル(1738-1822) Sir Frederick William Herschel |
|||
劇的セレナータ「シピオーネの夢」(1771) Il sogno di Scipione |
プラトン→キケロを台本とした古代宇宙観 |
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト
(1756-1791) Wolfgang Amadeus Mozart |
||
太陽四重奏曲*(1772) Sonnen - Quartette Op.20 |
出版社がつけたタイトルで実際には無題 |
フランツ・ヨーゼフ・ハイドン
Franz Joseph Haydn |
||
フィレモンとバウキス またはユピテルの地球への旅(1773)+ Philemon und Baucis, Hob.XXIXa:1 |
マリオネット・オペラ(人形劇) |
フランツ・ヨーゼフ・ハイドン
Franz Joseph Haydn |
||
歌劇「月の世界」(1773) Il Mondo Della Luna |
ジョヴァンニ・パイジェッロ(1740-1816) Giovanni Paisiello |
|||
歌劇「月の世界」(1775) |
ジェンナロ・アスタリータ(c1745-1805) Gennaro Astarita |
|||
歌劇「月の世界」(1777) Il Mondo Della Luna |
Carlo Goldoni台本 |
フランツ・ヨーゼフ・ハイドン Franz Joseph Haydn |
||
交響曲第41番「ジュピター*」(1788) Symphonie No.41 |
出版社がつけたタイトルで実際には無題 |
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト Wolfgang Amadeus Mozart |
||
弦楽四重奏曲第78番「日の出*」(1797) String Quartet in B-Flat Major, Op. 76-4 |
出版社がつけたタイトルで実際には無題 |
フランツ・ヨーゼフ・ハイドン Franz Joseph Haydn |
||
いまや輝きに満ちて、陽は光を放ちながら昇る(1798)+ In splendour bright is rising now the sun |
オラトリオ『天地創造』より |
フランツ・ヨーゼフ・ハイドン Franz Joseph Haydn |
||
空と星々(1799)+ El cielo y sus estrellas |
声楽。作詞不詳 [Orchid Classics: ORC100208] |
エステバン・サラス・イ・カストロ(1725-1803) Esteban Salas y Castro |
||
編集後記(更新履歴) - 2023/06/17- |
|天文学史と音楽史| |

|中世 - 1700|1701-1800|1801-1900|1901-2000|2001 - |
(上記リストの他、作曲年代の不明な楽曲のリストもごらん下さい)
|天文学史と音楽史| 星のささやき、宇宙のうた|

