�b���ƓV�E�̉��y�Ɓi���̃\�����G�̃u���O�j�b
�t�B���b�v�E�J�b�T�[���̃}���\���E�R���T�[�g
| �@�����z�z���ꂽ�v���O�����ɃJ�b�T�[�����̃e�L�X�g���|��Ă��܂����̂Ť�]�ڂ��܂��B �@���ꂩ��J�b�T�[���̃y�[�W�Ōf�ڂ��Ă���A���o���W���P�b�g�ւ̃T�C���ͤ��1���I����ɁA�����ɏo�����悤�ƃu���u�����Ȃ���M���҂����Ă���Ƃ���փJ�b�T�[������1�l�ŏh����̃z�e���֖߂�i�����ł������Ƃ�������Ă��j�Ƃ���֏o���킵�܂����B�ނ��M���҂����Ă��Ĥ�ꏏ�ɒ����ɗ����m�l�Ɂu�˂��A������������c�v�Ǝw���������ɖڂ����ƃ|�c���ƐM���҂�������s�A�j�X�g�B�Ƃ����킯�ŁA�H��T�C���ƂȂ�������ł��B�������킹�̃A���o�����ׂĂɂ��Ă�������̂Ōv7���I�u�Ӂ`���v�Ƃ������Ȃ�����T���T�����Ə����Ă��������܂����B �@�܂��A�K���Ȃ��ƂɎ��ׂ̗ɃJ�b�T�[�����̃}�l�[�W���[����4�����璅�Ȃ���܂����B�ŏ��ׂ͗̐Ȃ���ȂŁA���������Ȃ��Ȃ��A�ȂǂƎv���Ă����̂ł����A��4���̎n�܂钼�O�ɍ������K�C�W���������J�b�T�[���Ɋւ��鎑�������Ă����̂Łu�ق�A�T�C���������������v�Ǝ������Ɍ������Ƃ���u���͔ނ̃}�l�[�W���[���v�Ƃ����ł͂���܂��I�u�ǂт�������v�ł͂Ȃ��u�ǂтシ�������v�Ƃ��������̎�قǂ�������i�j�A��A�̃R���T�[�g�ł̎��]��ǂ܂��Ă��������A���{�����̃v���O�������y���y���̃R�s�[�ꖇ���������Ƃɕ��S���Ă݂���i��������������ꗿ�̋��z����������Ƃт����肵�������j�ƁA�Ȃ��Ȃ��M�d�ȑ̌��������Ă��������܂����B |
�y1��4��̃��T�C�^���z |
�@�N���[�h�E�h�r���b�V�[�̃s�A�m�̂��߂�80��i�S�̂��A������1���̂����ɉ��t����Ƃ������Ƃ́A �ނȂ����p�t�H�[�}���X�ł��A�}���\���ł��Ȃ��āA�ǂ��ɂ���`���Ȃ����낵���������Ɏ��Ă���B���̗��́A������ėǎ��ŁA��ɈӊO�������茻��I�ȉ� �F�A���͋C�A�����ĕ��i�ɂƂ�킯�x���E�̐_���ւƗU���A���̑S�Ă̗̈�ɓn���āA��X�͈�C�Ɏ�ɓ���邱�ƂɂȂ邾�낤�B�Ƃ����̂́A���̂悤�� �c��ȍ�i���W�߂��Ă��A���̂Ȃ��ɂ́A���܂�d�v�łȂ���i�Ƃ��A�ƂƏ̂����悤�ȍ�i�́A�قƂ�ǂȂ�����ł���B���̉��y��@�́A�₦���Ƒn�I �ŁA�����ŁA���f�I�ŁA�C�i�����艹�F�́A�߂܂��邵���l�X�ɕς��̂ŁA���̑S�ȉ��t������ɂ�āA�������v���Ă�������͂邩�ɂ����Ƒ����A ��X�̊���Ɗ��o�ɏP����B����͏^�A�����Ɋ��o�I�Ȋ�сA�D��S�A���ɐg���䂾�˂邱�ƁA�C���炵�A�������R���[����������������̂Ȃ̂ł���B �@ ���̂悤�Ȏd���Ƃ��ꂪ����������̂��A4�̗[�ׂɂ��ɕ�����A�����̖`���I�ȋ�Ԃɋy�ڂ����͂Ɩ��͂��m���ɑ��Ȃ����ƂɂȂ邾�낤���A�Î~ �������Ԃ��邢�́A�͂��Ȃ����Ԃ̊T�O�A���G�ő��w�I�ȃ��Y���̊T�O�A�ω�����ȁA�ґz�I�ŁA������ȉ��F�Ə̊T�O�ɂ��āA�h�r���b�V�[������ ������ނȂ��d�����\���ɑ����邱�Ƃ��ł��Ȃ����낤�B���̉F���������ł��߂܂��邽�߂ɂ͋t�ɁA�����ʂ�̈Ӗ��́A�ؔ����������A�������I�ȋZ���Ȃ��� �͂Ȃ�Ȃ��B�S�ȉ��t��́A4�̃��T�C�^������Ȃ�A�ŏ���3�͋x�e�Ȃ��ɍs���A���ꂼ�ꂪ�ЂƂ̃e�[�}�ƁA�h�r���b�V�[��e�ՂɌ��т��邱�� ���ł����l�̍�ȉƂ��߂�����̂ł���B �@�ŏ��̃��T�C�^���́u�����[��]�v�ł���B���́A�h�r���b�V�[�����h���Ă�����ȉƂ� �Ƃ����Ă݂����̂ł���A19���I���ƍ����I�����̃t�����X�l�̉��y�Ƃ������Y�ꂽ���Ƃ̂Ȃ��A�o���b�N�ƌÓT�h�̋������̂�����̂ł���B2�Ԗڂ̃��T �C�^���́A�h�r���b�V�[�̗��K�Ȃ̉��y���A������̂ɂƂ��ẮA�����ɁA�˔�ŁA�����I�ŁA���܂��ߊ�����̂ł��邩�ǂ����A�������Ƃ������̂ł� ��B����͂��傤�ǁA���@�[�O�i�[�̉��y���A���������������̂Ɠ������B���@�[�O�i�[�̏ꍇ�ɂ́A�s�v�c�Ȃ��Ƃ����A�h�r���b�V�[�I�Șa���Ɖ��F�̒T�� ���A���łɂ͂�����ƒ�������̂ł���B |
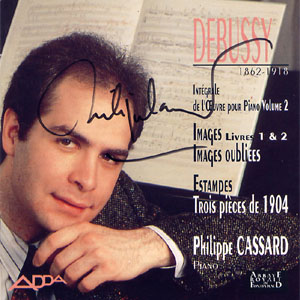
�y�h�r���b�V�[��24�̑O�t�ȁz |
�@�u�O�t�ȏW��P�W�v�́A���ɒZ���������ɁA�܂�1909�N12������1910�N2���ɂ����č�Ȃ��� ���B�h�r���b�V�[�́A�ʏ�A��i���d�グ��̂Ɏ��Ԃ�������̂����A����̍�i�́A�����āA����1�Ȃ���Ȃ����B�u��Q�W�v�́A�����炭�A��芮���x �������A��ɂ��郌���F���̃C���X�s���[�V�����Ɛ���������Ă���A�����Ǝ��Ԃ����������i1910�|1913�j�̂����A���̂Ƃ��h�r���b�V�[�͕��s���� �w�V�Y�x�Ɓw���Z�o�X�e�B�A���̏}���x�Ɏ��g��ł����B��ȉƁA�����ă��b�J���h�E���B�j�G�X�i�h�r���b�V�[�̈̑�ȗi��҂ł��艉�t�Ɓj�A�t�����c�E ���C�r�b�q�A�m���E�h�D���E�F�b�g�A�W���k�E�����e�B�G�Ƃ������s�A�j�X�g�����́w�O�t�ȁx�𐔋Ȃ̃O���[�v�ɕ����āA1910�N5������12���̂����� �ɏ��������̂ł������B �@�����́w�O�t�ȁx�ɂ���āA�h�r���b�V�[�̓o�b�n�i�w���ϗ��N�����B�A�� �W�x�́j�ƃV���p���̉�����Ɉʒu�Â���Ȃ�A�����āA�����Ƃ��Î��I�Ȋϓ_���猩��A���@�[�O�i�[�̉�����Ɉʒu�Â���Ȃ�A�����̌`���Ƙa�� ��̘_���ƓO��I�ɒf�₷�邱�ƁA�s�A�m�̎������̉\�����_�ɒT�����邱�ƁA�����āw�f���x�̑�2�W�ɂ��łɖ��炩�������u�_�ɂ��W�J�������v �i�W�����P�����B�`�j���邱�ƁA�����̂��߂ɁA�����A���܂��ɁA24�́w�O�t�ȁx�̑唼�́A�Ƃ��ɂ͊A�a�Ƃ�������قǁA����߂Č���I�Ȃ��̂ɂȂ��� ����̂ł���B �@���̏�A������`������鉉�t�Ƃɂ���Ĉێ�����Ă����A��Ȉ��̇��h�r���b�V�[���̂ڂ������ƁA���l�A���m���[���A�h�K�A���邢�̓^�[�i�[�̂悤 �Ȑ��҂Ƃ������A��ێ�`�^���̉�Ƃ����́A�����������A���G�ɊW�t�����Ă����B�m���ɁA���҂́A���鎞���A�݂��ɊS�������Ă������A�ނ�̊G�� �̎���߂����A���F�ɋP���A����`�́A���邢�̓��F�[�������������悤�Ȑ����ɂ���āA���̎Ⴂ��ȉƂɉe����^�����������̂ł���B���̂悤�ɍl���� ���܂��ƁA1910�N���̃p���ɁA���m�̃��Y���ƐF�ʂ��ǂ��ƌ��ꂽ�Ƃ������Ƃ��y���ɂ��Y��邱�Ƃɂ���B���I�[�̔ߌ��I�Ȋ��o�ƕM�v�̌��݁A�L���r�X ���̕��A�s�J�\�̃o���G�ւ̔M���Ɣ����Ƃ����፷���A�}�e�B�X�ْ̋����̂���V�N���A�X�g�����B���X�L�[�A�t�@�����͌��킸�����ȁA�����ċɓ��̉��y���� �p���͌��o�����B����炷�ׂĂ��A�����A�����̉��y���蒆�ɂ��Ă����h�r���b�V�[�̂悤�ɁA�s�������������Ă����l���A���ہA�������͂��͂Ȃ��B �@�h�r���b�V�[���A�w�O�t�ȑ�2�W�x�S�̂��A3�i�̕��\�Ɂi�`���̃y�[�W�� �́A���ۂɂ͎g��Ȃ��������̂́A�S�i�̕��\�����g���āj�������Ƃ����A�ꌩ�d�v�ł͂Ȃ��������w�������Ă���̂́A�I�[�P�X�g���ւ̊g��Ƃ����\�z���� �ł͂Ȃ��A��ԁA���ԁA���f�ނ��������킳��āA�N���o��ɂ��������āA���܂����ĂȂ��قǁA�L���ȓ����������A���G�ɂȂ��Ă��܂����̂ŁA���܂苷�� �g�g�݂̒��őg�D���A���炩�ɂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����Ƃ����ӎ��Ȃ̂ł���B �@�p���f�B�[�C���A�ٍ���̓��e�A�y�₩�ȋC�i�����łȂ��A�ł����C�̂��� �O�t�Ȃ̍ˋC���A��1�W�A��2�W�̓����ł́A�e���|�̒x���O�t�Ȃ̂������ɁA���p���̂��߂̃]�[���̂悤�ɕ��z����Ă���B�x���O�t�Ȃ́A���́A����2�� �̋ȏW�̒��ł��^�ɓV�˓I�Ȍ��삾�B�ґz������A���_���W�������肷��̂ɓs���̂悢�A���̂Ă�ꂽ�A���̂Ȃ��L��ȋ�ԂƂ����ׂ��A�����̃y�[�W�́A �ǓƂƎ��]������A�ɂȂ������͋C�������o���Ă���B���̌o�߂́A�����ł́A�قƂ�NJ��m����Ȃ��B�苿���ቹ�ƁA�K���I�Ȋ��o�̂�����肵�� �g���݂̂��_��I�ȌĂѐ��̂悤�ɐ[��������K���B���I�����鎞�ԁA���ށA�p�ЂƂ����Œ�ϔO���iH.�n���u���C�q�j�ɓ˂���������āA�h�r���b�V�[ �́A�������������i�Ɖߋ��ցA�a�፷����������B�u�f���t�H�C�̕��P�v�A�u���߂鎛�v�A�u�͂�t�v�A�u���̌����������e���X�v�A�u�G�W�v�g�̒فv�ɂ� ����悤�ɁB�܂��A�u�����̌������́v�̔j��悤�ȁA�ۉ��Ȃ��ɂ͂�����悤�ȉ��A�u���n�镗�v�̈Ӓn�̈����A���������A�u�r�[�m�̖�v�̓��ɔ� �߂�ꂽ�\�́A�u�ԉv�̓��˂ɂЂ��炩���ꂽ�A����ꂪ�Ȃ����̂悤�ɑ��������B���g�D�I�W�e�B�A�����ɂ́A���߂��悤�ȁA���邢�͑��l�܂�悤�Ȃ� ���낪����B �@��Ȃ��ƂɁA�h�r���b�V�[�́A�ǂ��炩�Ƃ����ƈÂ����y�S�̂��A���邭�� �悤�Ƃ���Ƃ��A��ɁA�O�I�ȗv�f�A���Ƃ��Γ����̃G�s�\�[�h��A�ÏL���p���n�̖��͂𗊂݂ɂ���B�`���ƁA�\���ƁA�F�ʊ��̏�ł̗ގ��ɂ���Ă������� �o�q�̌Z��̂悤�ȁA��1�W�́u�����F�̔��̉����v�A��2�W�́u�q�[�X�̑��ނ�v�݂̂��A�����炭�A���₩�ȃh�r���b�V�[�̑f�p�ŁA�T���߂Ȕ��f�Ȃ̂��� ���B |

�y�g�Ȃƕ��ȁz |
| �u�q���̗̕��v��2�̕��ȁi�u�����g���x���v�Ɓu�����ȍ��l�v�j�𖾂炩�ȗ�O�Ƃ��āA�v���O������3���̍�i�́A1903�N���O�ɏ����ꂽ���̂ł���B�������Ȃ���w�x���K�}�X�N�g�ȁx�i1890�j��w�s�A�m�̂��߂Ɂx�i1894-1901�j�̒��Ńs�A�m�ɂ͂�����ƕ\��Ă������̂����鍭�Ղɂ�������炸�A��Ȃ��ƂɁA�������́A������́u�Y���ꂽ���S�v�i1887�j�A�u�₩�ȋ����v�i1891�j�A�w���y�l�d�t�ȁx�i1893�j�A�w�q�_�̌ߌ�ւ̑O�t�ȁx�i1894�j�̂悤�ȁA����߂Ď��̍������z�ɂ��A���ɓ��O�ɍ��グ���A�Ջ@���ςŁA�O�ꂵ�Ďa�V�ȁi���������ĉߋ��̍S�����������ꂽ�j��@�ɂ�錆�삩��́A�قlj����Ƃ���ɂ���B �@���ہA�V���p���A�V���u���G�A�r�[�[�A�t�H�[���A���@�[�O�i�[�A�{���f�B���A���\���O�X�L�[�̉e�́A���X�ɁA�p���������A����������e���̏Ƃ��������A�h�r���b�V�[���A�D�݂̊y����g���āA���F�A�F�ʂ̐k���A���ԋy�ё�_�ŁA���i�Ȓ�������J�����ꂽ�a���̓W�J�Ɋւ���v�V�Ɏ��g�ނ̂ɁA������A�x����Ƃ����Ƃ������Ƃ̏Ȃ̂ł���B �@18�ۂ̎�҂����߂Č��U����Ȃ��������u�{�w�~�A���ȁv�́A�X���u���̂Ђ�߂��ɂ���i�ŁA�h�r���b�V�[�̗i��҂ł�����t�H���E�����b�N�w�l�ɂ���ă`���C�R�t�X�L�[�̔��f�Ɉς˂�ꂽ�B“�����ł́A�����Ȃ�v�l���[�߂��Ă��Ȃ��B�����ɂ͌`���������Ă���”�w����݊���l�`�x�̍�҂͂����������B�m�łƂ����u�}�Y���J�v�i1885�j�́A�V���p���̎�ʂ̂悤�ȍ�i�ւ̏����Ⴆ�Ȃ���^�����A���˂Ȋ����̒���Ɗ���̑�_�ȕω��́u���}���e�B�b�N�ȃ����c�v�i1890�j�̌��ƂȂ��Ă���B�u�X�e�B���[���̃^�����e���v�́A�s�A�m�̂��߂̍�i�ł͗ތ^�ɑ������A�ŏ��̓Ǝ��̂��̂ł���A�����ł�����ׂ�ȃX�P���c�H�̓r���ŁA�u�}�X�N�v��\������悤�ȁA�a�炰��ꂽ�a���̕��G�Ȍ��т����A���Â�ɂȂ����悤�ɕ�������B �@���̎��R�Ȓ��q�Ɛe���݂₷����ނɂ���āi�w�O�t�ȏW�x�̍Ō��ʂɂ��ĉ₩�ȕ����͂Ȃ��j�A�w�x���K�}�X�N�g�ȁx�́A�]�����ƌ����Ȃ��܂ł��ЂƂ̒i�K���L���Ă���B�S�̂͋C�܂���ŁA���z�Ƌ}���ȕω������蔲����悤�Ȃ��̍�i�́A�l�X�Ȍ`���Ɛ��@�ƁA�ȑO�g���Ă���������^���āA�I�݂Ɍq�������̂ł���B�u���̌��v�́A��������āA���̂���߂����I�ȏ��@�ɂ���āA�u��т̓��v�A�u���ɉf��e�v�A�u�X�P�b�`�����v�𖾂炩�ɐ��肵�Ă���B�@�ׂł̂�т肵���A4���q�́u�p�X�s�G�v�́A�������O�ŁA3���q�ɂ��̂̉����ȕ��ȂƂ͉��狤�ʓ_���Ȃ��Ƃ������Ƃ��킩�邾�낤�B1894�N����1896�N�ɂ����čl�����A1901�N�ɏo�ŁA���b�J���h�E���B�j�G�X�ɂ���ď������ꂽ�A�͋����g�ȁw�s�A�m�̂��߂Ɂx�́A�ΏƓI�ɁA���l�|�I�ŃI�[�P�X�g�����̑��ʂ������Ă��邪�A���ꂪ��i�S�̂̕]�����グ�邱�ƂɂȂ����B�ÓT�I�Ȍ`���ɂ��A3�Ȃ̂��̂��̂��A�n�ӍH�v�炵�����@�ɂ���čۗ����Ă���B�Ƃ��ɂ͗��ꂽ���S�a���̕��u�A���s4�x�A���s7�x�A9�x�̘A���i�����ł́A�S���V���������I�j�A�|�����̑@�ׂ��A���̕����I�Č��A���Y���`�̑��p���Ƃ��������@���B�u�O�t�ȁv�̎��X�ȘA�ł̌�ɁA�u�T���o���h�v�̑��d�ŁA���������悤�ȕ\���͂��������A����̓����F���ɂ����1903�N�ɃI�[�P�X�g���ȂɕҋȂ��ꂽ�B�u�g�b�J�[�^�v�́A���C�����ς��A�܂䂢����̏�Ȃł���A�N�[�v������X�J�����b�e�B��M���Ƃ����A���Ă̋������v�킹��悤���B �@“�@�ׂȗd���̏����ȉ���”�i�g.�n���u���C�q�j�Ƃ���ꂽ�w�q���̗̕��x�́A�h�r���b�V�[�̃s�A�m��i�̒��ŁA2�́w�f���x��24�́w�O�t�ȁx�̊Ԃɒu���ꂽ�}����̂悤�Ȃ��̂��B�w�f���x�Ɓw�O�t�ȁx�́A�w�y���A�X�ƃ����U���h�x�ƂƂ��ɁA���ۓI�ȉh�_�ւƑ傫���O�i�����̂����A�^�ɗ������ꂽ�킯�ł͂Ȃ������B�h�r���b�V�[���A1908�N�ɂ�3�����������̖��A�V���E�V���E�ɕ����Ă����A�Ђ��ނ��Ȉ���A���̍ז���̂悤�ȍ�i�̑g�Ȃ������炵�A����́A�V���[�}���́w�q���̏�i�x��A�t�H�[���́w�h���[�x�A���\���O�X�L�[�́w�q���̂���̎v���o�x�́A���X�Ƃ�������̒��ɂ���B�~悁A��������A�����̃Q�[���A�����ꂽ���t�A�������R���[�A�����čŌ�̃s���G�b�g�A����炪�A���܂��v������A�y��̐��������g�������W�߂��ԑ��̒��Ō��э��킳���B�h�r���b�V�[�͏�ɁA������̉��y�I�ȐV�@���Ɏ����X���A���m�ȁu�S���E�H�b�O�̃P�[�N�E�H�[�N�v�ɂ����ẮA���m�̃N���V�b�N���y��i�ɏ��߂āA�W���Y�̃��Y���ƕ��͋C���������B���̋Ȃ̒��ɂ́A����ɁA���@�[�O�i�[�́w�g���X�^���ƃC�]���f�x�̃p���f�B�[�����p�����荞�܂��Ă���̂��I �@�u�����ȍ��l�v�i1879�j�́A�����炭�͐����ƁA�V���u���G�Ɉ������������ꂽ�A�u�S���E�H�b�O�̃P�[�N�E�H�[�N�v�̂������葁����p�i�̂悤�Ɍ�����B1910�N�ɂ́A�h�r���b�V�[�́A“�����v����y���Ă���킵�������肽�����o�������Ȃ��e�B�[�E�^�C���̂��߂ɁA�J�t�F���X�g��������”���}���e�B�b�N�ȁu�����c�v����Ȃ����B�������́A“����߂ăe���|���o�[�g�ŁA���炩���������āA��M�I��”�g�D���[�Y�����[�g���b�N�ƃ��m���[���̍x�O���X�g�����̒��Ԃ̕��͋C�̒��ɐZ���Ă���̂��A�ˑR�ɂ킩��̂��B |
�i���n���q��j |
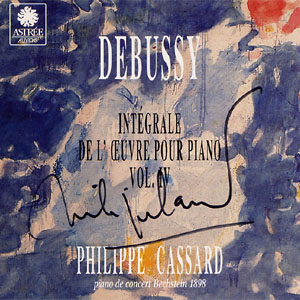
�bnext�b
�b���ǂ�i�t�B���b�v�E�J�b�T�[���̃h�r���b�V�[�j�b�����f�B�b
�b�h�r���b�V�[�̃s���I�h���t�b�h�r���b�V�[�̐��E�b
�bhome�i��Ԑ��̂Ȃ�j�b
