|星と天界の音楽と(星のソムリエのブログ)|
|
| 『日本書紀』(720)の中で景行天皇 五月壬辰朔、従葦北発船到火国、於是日没也、夜冥不知著岸、遙視火光、 (訳) |
これを読むかぎりでは景行天皇が見た光は、ちょっと冷静になって考えてみれば、陸の光であることがわかります。しかし後に伝えられることになる史実では、この火がいわゆる“不知火”としての伝説となったという興味深い記述となってしまったのです。
|
| 『高子観遊記』(1720) 天皇問其火光処、国人対曰、是八代県豊村、亦問是誰人之火也、不得其人、 茲知非人火、故名其国曰火国、火国後改作肥国、於今為前後二州 審如史臣所紀、則其国以火為名之故耳、非不知火之言也… (訳) |
| 『水産界427号』(1910) 島原において当時長崎測候所長築地宣雄氏は、島原中学校長、主席教授とで不知火と呼ばれている火を経緯儀を使って観測した。そして対岸地方の警察署に依頼して、当夜漁船が出たかどうかも調査した。そして不知火と呼ばれていた火がその日に出ていた漁火だということがわかった。しかし昔から有名な島原地方の伝説を破棄することになるので、その結果は発表しなかったのである。 |
この1910年の『水産界』の記述は非常に興味深いもので、事実を公表してしまうと“島原地方の伝説を破棄することになる”という意味合いから発表しなかったとしている。そして以後の調査などで、不知火の正体は明らかにされる。
|
| 『不知火探検隊』藤森三郎氏 “三時五分陸上観測所より、汝(千鳥丸)の付近に不知火出現す、調査せよとの煙火信号あり、代って直ちに火団に接近すれば、案の如く時恰も大干潮時にて、露出せる干潟上に、左腕に松明またはカンテラを持ち、右手に鳶口を握り、腰に径二尺ほどの桶を曳きたる漁業者が右往左往して、タイラギを漁りつつあるを認めたり。午前四時十分に至り、潮水潟上に上来ると共に、彼らは漸次火を消して船に上り、四時四十分には全く消滅し、僅かに船上に暖を取る暖¥炉火の四五個を見るのみとなり、上げ潮と共に帰途につき、未明に全く帰宅し、夜明けとなれば、一隻の漁船だになし。茲に当夜半午前三時三十分の官庁を中心とし、貝類、主としてタイラギを採集する漁火を指して、不知火となすものなることを確実に証明することを得たり” |
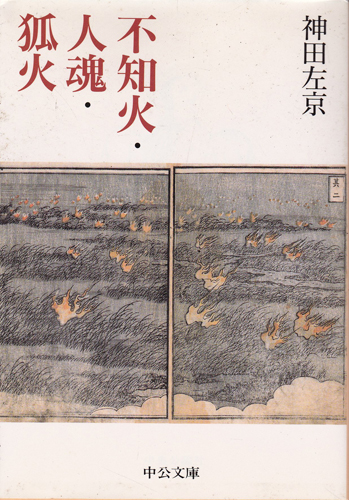 |
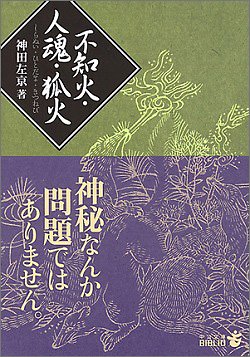 |
| 『不知火・人魂・狐火』(中公文庫・1931)神田左京 “これは結局不知火の問題ではありません。人間の問題です。不知火の正体見たり漁夫の火。”(P275「14 結論」より) ※2005年に中央公論社から新版が出版されました |

| 『不知火新考』(築地書館・1994)立石巌 八朔(旧暦8月1日)は、稲の収穫を目前として豊作祈願や予祝に関連し、いろいろ進物の贈答のある日で、武家の食前には魚介から新鮮な野菜がたくさん盛られていた。 つまりこの日は正月に次ぐ重要な祝典の意味を持ち、魚介がたくさん求められ、それがこの海の干潟と十分関連のあったことが推定される。数多くの灯が、この海を飾ったということも、この日のみに出現する不知火なる日と関連があったことが考えられよう。 不知火の光源とされるものは、石油が使われる以前は松明であり、何の覆いも付けていなかったので明るかったが、燃料が石油に取って代わると火種が消えぬようにということで四角い覆いが取り付けられるようになった。この時点で不知火の明るさが暗く、規模も小さくなったようになったという。つまり明治15年頃から、石油ランプが漁火に使用され、このため漁夫はがん灯を作ってそれで海底を照らしていた。このため、光の強さが衰え、長い間不知火が観測されたことがなく、不知火見物が消滅しつつあった。 しかし、明治以来石油ランプがほとんどであったのが、戦争が起こったためかアセチレンランプになり、再び盛大化した。 しかし、水俣病の原因となった日本窒素(チッソ)の進出により、汚染物質の垂れ流しが問題となって、この付近一帯の干潟での魚貝採りが敬遠されたことも手伝って、以後不知火の発生も激減することになる。 |
『不知火・人魂・狐火』(中公文庫・1931)神田左京と『不知火新考』(築地書館・1994)立石巌を読んで、僕は膝を叩いてしまいました。まさに「目から鱗」というやつ。事実を知ることができて嬉しかったという意味。特に前者は不知火に限らず、日本で怪火と怖れられた狐火、鬼火、人魂、火柱、火の玉、不知火など、自然界における不思議な怪火という現象を徹底的に検証し、化学的実証を試みた科学的古典です。 よくぞ1000年以上もの間、怪火とされた現象を冷静に紐解き、その結果、様々な事象が結びついて世にも不思議な、そして千年もの時を生き続けてきた不知火を解明してくれたなと! 残念な点を上げるとしたら、その怪火がほとんど過去の出来事になってしまったということでしょうか。さらに言えば、温暖化による温度の上昇が拍車を掛け、最初に書いたように「絶滅」に脅やかされてしまったことです。 |

昭和52年9月14日(熊本日日新聞)

平成元年8月31日(熊本日日新聞) |
“ここに述べた肥後の不知火は不知火海中の鏡海の海水の温度が特に高いことに起因して、毎年八朔の午前二時より四時に至る間に現れ、そのときを違えないのは、この干潟、朝夕、季節、漁法、見方などの条件がそろって不思議な現象が起こることは科学的にも神秘的ではあるまいか” ・下層が冷たい場合の蜃気楼 |
『不知火考』(天保6年)中島廣足 はじめ火の間やや離れて見ゆるをようようその間々に大小の火どもいでて、つぎつぎかずそわりゆくに、暁にいたりて盛なるときは海上一つつらにつらなりて見ゆ。その光また大小のさますべて星の如し。大かた横さま二里ばかりも連なれり。かくていよよ盛なるに、ほどなく東の空しらみて、夜も明けゆけば、その光に気たれて、ようよう火きえゆく。明けたてぬれば、あともなし。 |
|もどる(不知火)|神秘の火「不知火」(熊本観光サイト)|
|home(一番星のなる木)|


