|
【ドビュッシー:5つの三部作】
1894年に作曲されたのに、1977年にようやく出版された、いわゆる『忘れられた映像』の三部作の作曲と、『映像第2集』(1907年秋)との間には、13年間の隔たりがある。ドビュッシー自身の言葉を借りれば、「ピアノと自分の対話」ということになるこの曲集は、重々しい雰囲気で、叙情味を含んだ、オーケストラ風の響きに満ちたノクターンで始まる。『ピアノのために』の「サラバンド」の元になるヴァージョンである、第2曲の冒頭で、ドビュッシーは、「重々しくゆったりとした優雅さをもって、少し古臭いポートレート、ルーヴルの思い出、云々…」と支持している。「もう森へは行かない」、つまり、「雨の庭」のおぼろげな先祖は、対照的に、生き生きとして変わりやすい色彩の斑点であり、陽気さと諧謔にみちた帰結なのである。 リッカルド・ヴィニエスによって、1904年1月に初演された『版画』は、ドビュッシーが十分に成熟したこと、彼が絶えず、異国の香りと響きと風景に興味を抱き続けていたことの痕跡をとどめている。“ぜいたくをして旅行をする手立てがないときは、空想で補わなければならない”と、ドビュッシーはメサジェに書いている。「パゴダ」は、五音音階のテーマをとおして、1889年の万国博覧会で賞賛されたバリの鐘とガムランを響かせる。「グラナダの夕べ」は、これらの膨大なピアノのためのノクターンの第1曲で、その和声はきわめて洗練されており、そこには、静寂、つまり、突然の大音響や、遠い祭りと儀式の反響によってしばしば妨げられる荒涼とした沈黙が、かわるがわる漂っている。ドビュッシーが一度も訪れたことのないスペインを思い起こさせる、この熱にあえぐようなハバネラは、マニュエル・ド・ファリャの賞賛を引き出すことになる。ある種のフランス的精神により近い「雨の庭」は、熱っぽいトッカータの足取りのもとに、囃子歌の詩の断片を隠しているが、それは、アルペジョの流れにのってフィナーレを迎えるときに再び現れる。 「スケッチ帳より」と「マスク」は、2曲ともドビュッシーのほとんど知られていない傑作であるが、それは、「喜びの島」の目も眩む明るさと陶酔感と対照的な、2つの夜の光景である。これらの3つの作品は、それぞれ、1904年に別々に出版された。「スケッチ帳より」の官能と疑問に満ちた、靄のような夢想に呼応するのが「マスク」の、苦悩に満ち、ゆがんだ幻想である。最後に「喜びの島」だが、ドビュッシーのあらゆるピアノ曲の中でももっとも豊かな内容を持つこの作品は、光と獲得された愛への長い旅であり、おそらくは、当時の彼の、エンマ・バルダックとの情熱的な関係を、きわめて外向けの寓話のとして物語るものである。1910年に、「スケッチ帳より」の初演を行ったのはラヴェルであり、他の2つの作品の初演は、忠実なるリッカルド・ヴィニエスであった。 『海』を仕上げてからわずかで、ドビュッシーは、『映像第1集』に取り組み、それは1905年末に出版された。“光の最後の詩、波によっておぼろになった光の詩”(アンドレ・スュアレス)というべき「水に映る影」が、玉虫色に光る多くの色彩に身を震わせると、沈黙と夜は、この深い水に囲まれた風景の眠りを誘い、風化させる。「ゆっくりと、重々しく、サラバンドの様式で、しかし厳格ではなく」と記されている「ラモーをたたえて」は、大理石のような気品と叙情の発露によって知られており、ドビュッシーが「優雅なインドの国々」の作者に限りなく寄せる敬意でもある。“気まぐれだが正確な軽やかさで”と、ドビュッシーは「運動」の冒頭に記している。要するに、切り込むような、絶えず動きまわり、滑稽な、そしてその展開の主要部分では陰影をつけられて、この動く永久機関は、航空機のように中空に消えていき、悟りきった道化のピルエットのように優雅なはかなさを湛えている。 『映像第2集』(1908)は、その書法の洗練の極み、過剰な響きの事象とリズムの複雑さ、その精神的な次元、その“音楽的時間の相対的で不可逆的な概念”(ピエール・ブーレーズ)によって、驚くべきものとなっている。どこから来るのかわからない音の断片に耳をそばだてると、この秋のメランコリー、つまり思い出を常にかみしめること、無に幻惑されることによって、「葉末を渡る鐘の音」とさらに「そして月は荒れた寺院に落ちる」の、瞑想的で非常に風変わりな雰囲気が醸し出される。「金色の魚」のきまぐれなおしゃべりが、オディロン・ルドンのパステル画から抜け出たような、新鮮な色合いと光のきらめきをもたらし、それは、ドビュッシーが書斎に所持していた、螺鈿と金の魚で装飾された黒い漆の日本の絵から着想を得た、この作品を通じてずっと続くのである。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
【練習曲、そして他の様々な作品】
既に病に犯されていたドビュッシーが、それにもかかわらず最後の創造的なエネルギーを振り絞って、ピアノのための12の『練習曲集』、2台のピアノのための『白と黒で』、そして2曲のソナタ(チェロとピアノ、フルートとヴィオラとハープのための)に真っ向から取り組んだのは、1915年の夏のことであった。突飛なところがあり、今日でもまだ神秘的で捉えどころのない『エチュード』は、ドビュッシーの30年代以降少しずつ、数多くの作曲家に参照され、啓示を与える崇拝の対象になっていった。バルトーク、ヴェーベルン、ブリテン、メシアン、バラケ、デュティユー、ブーレーズ、シュトックハウゼンや、ビル・エヴァンス、セロニアス・モンク、エロル・ガーナーといった人々だ。 まず、『練習曲集』の中には、ショパンに対する敬意があることは確かである。ドビュッシーはショパンを敬愛していたし、このころまさに、ジャック・デュラン社のために作品の校訂をしていたのだ。この曲の場合、技術的な困難が、楽器のイディオム(三度、オクターヴ、反復される音、などなど)をめぐって数多く使われ、サディスティックなのは確かなのだが、それらは決して露骨ではない。実際は、腕力や露出趣味ではなくて、軽やかさやすばやい反応を要請するものである。若かりしショパンの劇場的なロマンティシスムに、ここで取って代わるのは、純粋で澄んだ、暗示や類推に頼ることのない、それ自身のみが目的であるような音楽と詩の世界なのである。 言い回しや構造が簡潔さ、さらに古典主義を装っているが、音楽思想の表現において、以下に奇妙な細分化が行なわれていることか、いかにおびただしい数の形態、ほんのわずか書かれた断片やモチーフがあることか、そしていかに多くの急激な変化、急な針路変更、広がり、省略、そして“気まぐれ”があることだろうか!そしてとりわけ、コラージュ、衝撃、音の密集、まさに驚くほどの振動、反響、洗練された和声進行、併置されたリズム、それらの打ち消すことのできない快楽、これらすべてが、遊びの精神に貫かれており、そのために、ある種の不安、悲しみ、孤独の雰囲気が損なわれることはない。(「4度音程のためのエチュード」、「半音階のためのエチュード」、「対比的な響きのためのエチュード」) 『エチュード』の作曲中に、ジャック・デュランに宛てた手紙の中で、ドビュッシーは、自分の作品の新しいところと、批判的な側面を十分意識している。“特別な響きの探求… そこには、聴いたことのないものが見出されるだろう… この音楽は、演奏の頂点を見渡すものだ… 和声の精華というかたちをとった厳格な技法…”『練習曲集』に数ヶ月遅れて書かれた「悲歌」のみが、その独白の悲哀によって、「対比的な響きのためのエチュード」の独立した風景を思わせる。すっかり塞ぎこんだ雰囲気の中で書かれて、「英雄の子守唄」は、ベルギー王アルベール1世の勇気を称えているものの、重い、執拗な、暗い行進曲になっている。1914年の戦争は、ドビュッシーの気力に、惨澹たる結果をもたらしたからだ。1909年には、独立音楽協会の機関紙が、ラヴェル、デュカス、ダンディ、ウィドール、レィナルド・アーン、アンヌモンド・トリヤ、そしてドビュッシーに、ハイドンの死後100年に際して、小品を書くようにと提案した。ゆっくりしたワルツで、軽やかでからかうようなスケルツォに変わるのだが、この洗練された細密画のような作品は、ちょうど、年長の名高い作曲家からは解放された空想を思わせる。「コンクールの小品」(1904年ごろ)は、要するに、皮肉っぽい、朗々とした作品だが、和音の困難な繋がりによって、パリ国立高等音楽院の初見の試験の受験者たちを苦しめた。ドビュッシー自身もそこの学生であったのだが! 「2つのアラベスク」(1888)、「夢想」、「バラード」、「夜想曲」この3曲はみな1890年の作品だが、ともに、ある清々しさ、フォーレ風の色彩、旋律の明白なかわいらしさを備えている。しかし、「忘れられた小歌」、「ボードレールの5つの歌」、「叙情的散文」、「華やかな饗宴」といった、同時代に作曲された歌曲の素晴らしいピアノ・パートのことを少し考えてもみよ。ここで和声的な発見は、数多く、贅沢な響きの装飾は、それ自身で充足している。これらの初期のピアノ・ソロのための小品の、楽器の組織のもつ貧弱な様相には、なんとなく驚かされるほどのことはある。これらの小品は、ほとんど抽象に近く、閃光のような『エチュード』の前兆とはまったく違うのだ! |
|||||||||||
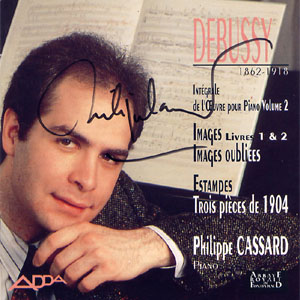 |
 |
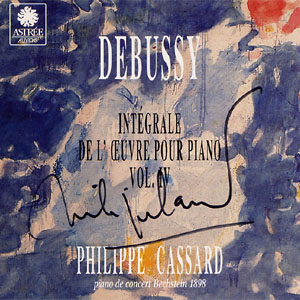 |
|||||||||
|
【組曲と舞曲】
「子供の領分」と2つの舞曲(「レントより遅く」と「小さな黒人」)を明らかな例外として、プログラム第3部の作品は、1903年より前に書かれたものである。しかしながら『ベルガマスク組曲』(1890)や『ピアノのために』(1894-1901)の中でピアノにはっきりと表れてきた個性のあらゆる痕跡にもかかわらず、奇妙なことに、私たちは、同時代の「忘れられた小唄」(1887)、「華やかな饗宴」(1891)、『弦楽四重奏曲』(1893)、『牧神の午後への前奏曲』(1894)のような、きわめて質の高い着想による、非常に入念に作り上げられ、臨機応変で、徹底して斬新な(したがって過去の拘束から解放された)語法による傑作からは、ほど遠いところにいる。 (恩地元子訳) |
|||||||||||