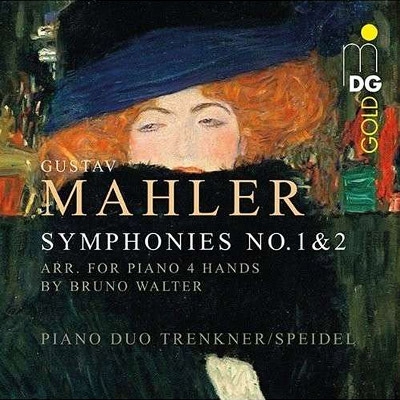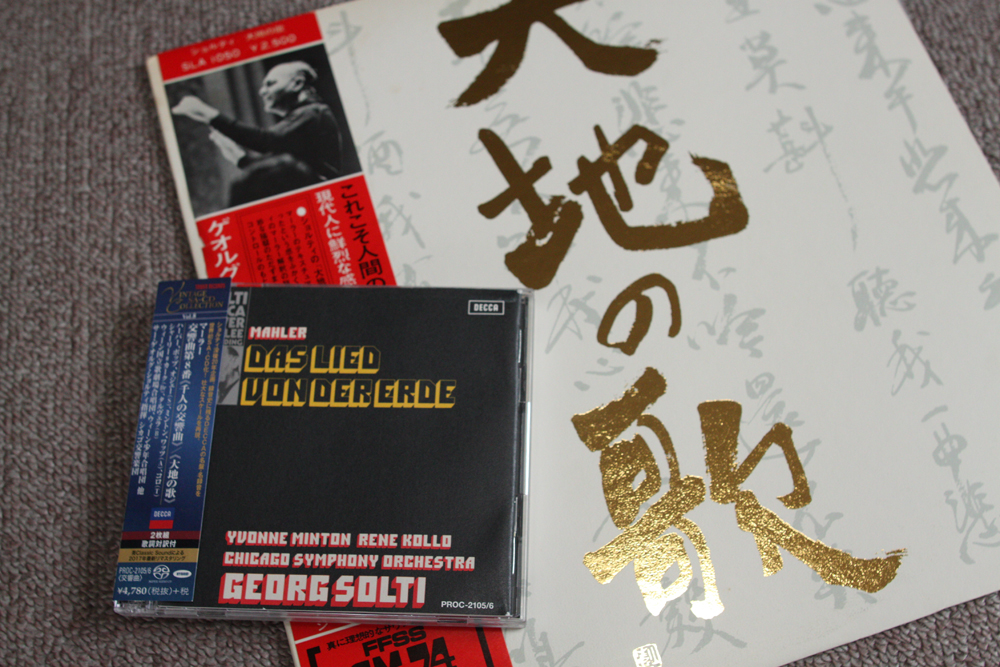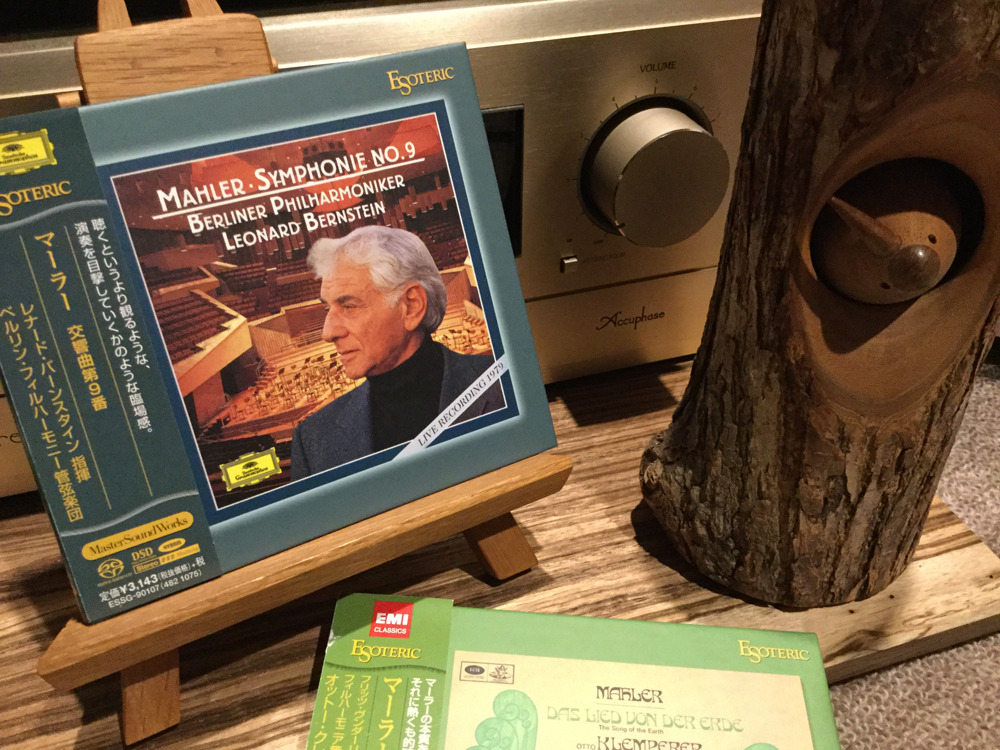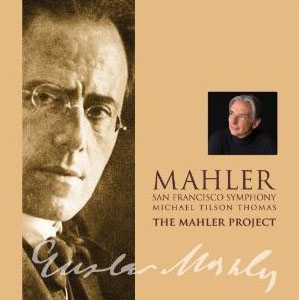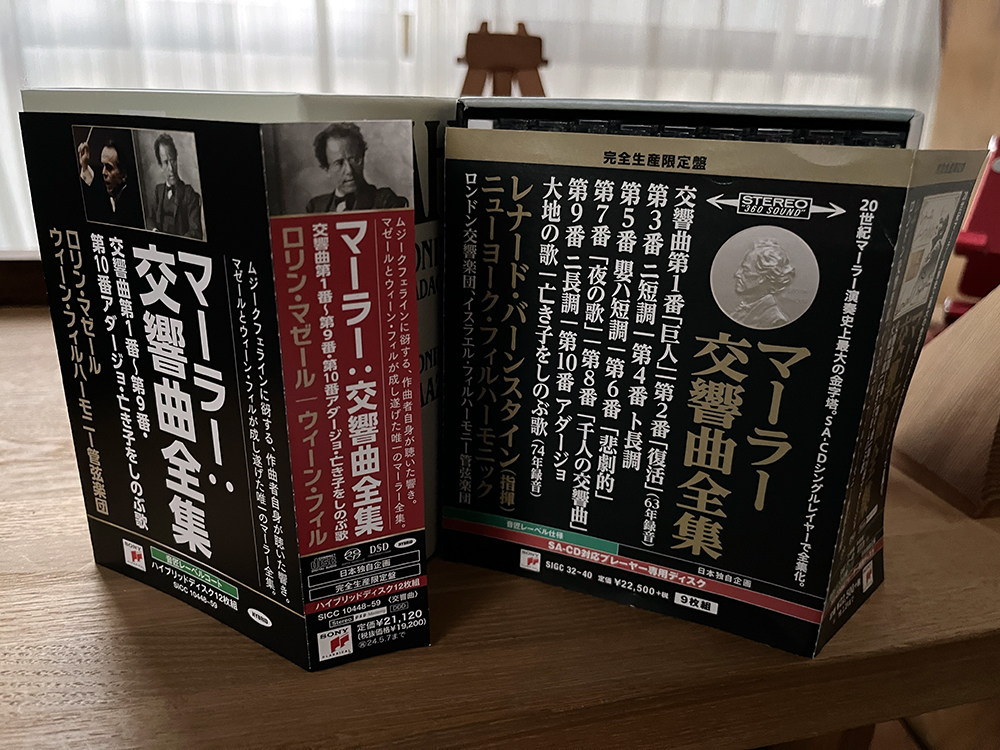|星と天界の音楽と(星のソムリエのブログ)|
| SACDの体験は、これを経験した人でなければわからない(当たり前ですが…)衝撃的な音場を体験させてくれます。これを体験してしまうと「もう普通のcdには戻れない!」と思ってしまうほどなのです。 マルチ・チャンネルを考えず、ステレオ(2ch)で良ければSACDを再生できるプレイヤーだけで、今までにない音楽で体験できるのです。というか、これが本来のレコーディングされた音? 「しかし!」マーラーのような立体的な音場をライブ会場で施すような作曲家の作品は、まさにマルチチャンネルでこそ味わいたいものです。 |
 |
| オープニングのオーケストラチューニングを思わせるような始まりが、徐々にカッコーの鳴き声を加えることによって朝もやの森を思わせる広がりへと広がっていく… 交響曲全体が、他の作品と比べると短いということもあって、彼の交響曲の中ではもっとも(一般リスナーにとって)人気のある曲でしょう。コンサートでもラストにはホルン奏者が立ち上がって声高らかに咆哮させるシーンはまさに圧巻! マーラーの作品は、彼の本職が劇場指揮者だったこともあり、ハーモニーを、実際のホールで鳴るときの具体的な音場を想像しながら作曲していたようです。 こうした効果こそ、このSACDのフォーマットで聴くにはうってつけの曲。派手に鳴らしても(第4楽章の冒頭!)耳がつかれず、音の洪水が体にしみこんでくるようです。、 |
|
|
 |
|
|
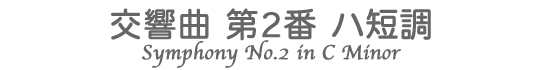 |
| 私がマーラーにはまったきっかけは、この曲から。「復活」というニックネームでも知られている大編成の曲で、途中ソロや合唱、バンダ(楽屋裏に控えているバンドで、遠くから聞こえてくる軍楽隊という想定)がこのフォーマットを更に面白くしてくれます。演奏者がどういう意図でこの曲を構築するかによって、コンサートホール的な響きから、リアスピーカーに音を振り分ける仕掛けを用意してくれるディスクもあります。特に私が好むマーラーは、大規模な編成であることはもちろんのこと、この曲のように合唱が加わるものが特にお気に入りです。 |
|
|
|
|
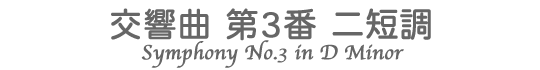 |
| 冒頭のホルン・ソロの歌は、それこそマーラーがワルター語ったように「(シュタインバッハの岩山の風景を)もう眺めるにはおよばないよ。あれは全部曲にしてしまったからね」という言葉通り、まさに目前に巨大な山がそびえているようです。 |
|
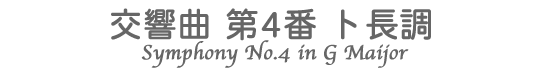 |
| 交響曲第1番と並んで、マーラーの交響曲の中でも比較的短い。第2番から始まった「角笛」シリーズの最終章で、第3番との共通点も多い。冒頭のカウベルも面白い効果があり、この雰囲気が全体の雰囲気も語ってしまっているかもしれません。第4楽章にはソプラノ・ソロ。非常に牧歌的な雰囲気がありますが、その内容は「無邪気」を通り越しています。ディスクによってはソロの立ち位置が異なるので、ディスクの聴き比べではそのあたりにも注目すると面白いです。 |
|
 |
| なんでも交響曲にニックネームのついていない曲で、日本では唯一「タイトルなし」でも集客のある曲なんだとか。やはり第4楽章:アダージェットのセンチメンタルなメロディと知名度(映画『ヴェニスに死す』)でしょうか? |
|
 |
|
マーラーの交響曲の特徴というか、私の好きなタイプは声楽つきの交響曲です。聴きはじめの頃は第6番、第7番がもっとも聴く機会が無かった曲です(「機会」と書いてしまいましたが、自分から近づかなかっただけ)特にこの第6番など純器楽曲はなかなか聴く気にならず。 |
 |
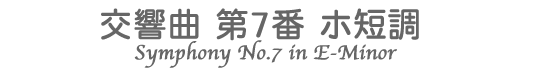 |
| ニックネームが『夜の歌』とすると、この曲の手引きになるのではないか、と思えるほど夜の持つ雰囲気を表現しているようです。マーラーの描くアニミズム的な夜の危うさも、SACDならではの臨場感たっぷりに、余裕で再現されています。 |
|
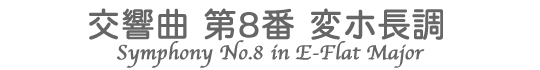 |
| SACDのマーラーで、真っ先に聞きたかったのがこの曲。オープニングのオルガンや合唱に、どれぐらいのスケールで取り囲まれるのだろう! |
|
 |
| ホルンの咆哮、それに対抗すべくテノールの雄叫び。6楽章すべてにソロパートの声楽を伴う異色の交響曲。大管弦楽を施しながらも、時折現れる室内楽的なハーモニーの対比。 |
|
|
|
|
 |
| ベートーヴェンの第九との兼ね合いから引き合いに出される「第九のジンクス」。もろ影響を受けたマーラーの第九ほど、それから逃れ、安らぎを得たいと思わせる楽想は非常に美しく感じさせてくれます。 |
|
|
 |
| この曲を初めて聴いた時は、その表示の番号(第10番)にも慣れていなかったこともあり、それまでのマーラーとは違う世界の音楽のように聞こえました。それも、いろいろな指揮者のレコーディングを聴くようになって(ラトルの影響かな)、だんだん第10番の悲しいほどに美しい響きに惹かれるようになりました。たった1楽章しか完成できなかったというエピソードも、聴く上では心理的な影響を与えてくれたようで、後半の不協和音の恐ろしいまでの響き。その響きが、SACDで聴く場合、強烈なまでに皮膚を通じて体の芯に入り込んでくるかのようです。 |
|
|
|
|
|もどる(SACDで聴く名曲たち)|home(一番星のなる木)|